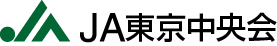【江戸東京野菜を語る ⑩ 】火山の島が引き受けた最後の畑~三宅島で早稲田ミョウガを育てる

東京は、暑くなりすぎた。
それは単に気温の問題ではない。ヒートアイランド、宅地化、担い手不足。土は細り畑は分断され、江戸から連なってきた在来野菜は、今や文化を語る以前に、つくり続けられるのか、という問いにさらされている。
早稲田ミョウガもその一つだ。江戸東京野菜として名を残しながら、東京の畑では夏の高温化で栽培が難しくなり行き場を失いかけていた。その時、選択肢として浮かび上がったのが三宅島での栽培である。黒い火山灰土と潮の匂い、台風の通り道でもあり、噴火と島民の全島避難も記憶に残る。人口減少と産業縮小の真っただ中にある島はあまりにも条件の厳しい場所に見えるが、それでも、早稲田ミョウガはこの島に託された。
なぜ、三宅島だったのか。背景には気候や土壌が適しているという説明だけではない。市場流通の論理に乗りにくい小さな産地でどうやって農業を続けるのか。「守るべきもの」と「稼がなければ続かないもの」をどう両立させるのか。早稲田ミョウガの移植は、そうした問いのすべてを包括する。語るのは三宅島農業振興会の代表理事会長、大年健士さん(66)。市場に出せば埋もれてしまう量しか作れない島で希少性のある作物をどう育てるのかを考え続けてきた。今回は一つの野菜をたどる物語であると同時に都市農業と島しょ農業のあいだに横たわる現実を一人の農業者の語りを通して掘り下げていくオーラルヒストリー、として報告する。
(聞き手:星槎大学客員教授・元東京都知事特別秘書 石元悠生)
三宅島に生まれ、生きる
― 生まれ育った三宅島で、噴火や全島避難を経ながらも農業を続けてこられました。振り返ってこの島で畑に立ち続けてきた時間は、どのような時間だったと感じていますか。

ついて熱く語る大年健士さん
「島で生まれて島で育って気がつけば畑が身近にある生活でした。特別に農業をやろうと意識したというより、それが日常の中にある環境だった、という感覚に近いかもしれません。高校を卒業してから東京農業大学の厚木農場で1年間実習を受けています。島の畑とは規模もやり方も違って初めて外の世界を意識した時間でした。
ちょうどその頃、愛知県のトマト栽培が盛んで、これは一度、現場を見ておいた方がいいと思って豊橋で研修を受けました。施設も整っていて流通も含めて産地として農業を成り立たせるという仕組みを間近で見ることができたと思っています。島で生まれて外を見てまた三宅島に戻る。振り返ると、その準備をしていた時間だったのかもしれません」
― 外の農業を知ったからこそ、三宅島に戻るという判断は簡単ではなかったと思います。それでも島へ戻ることを決めたとき、最後に背中を押したものは何だったのでしょうか。
「戻るというより、島でやるしかなかったという感じです。外に出て農業の現場をいろいろ見ました。規模も大きいし、施設も整っているし、流通も含めて産地として農業が成り立つ仕組みがきちんとできている。正直、ああいう形のほうが、農業としてはやりやすいだろうな、という思いはありました。それでも、じゃあ自分はどこで生きるのかと考えたときに、最後に残ったのは三宅島だったのです。いま振り返ると感情で決めたというよりも、ここでやらなければ、この島の農業は少しずつなくなっていく。そういう現実を、外を見たからこそ余計に実感したのだと思います」
時代と共に農業と作物が変わる現実
─ 父の代、そして自身の代と畑で作るものは変わってきました。それぞれの時代で、この作物を選ばざるを得なかった理由についてはどう感じていますか。
「父の代はレタスやセロリでした。当時は、それが三宅島で現金になる野菜だったのだと思います。島の条件で、どうすれば農業として成り立つかを父なりに考えた結果だったのでしょう。その後、時代が変わって、テッポウユリをやるようになり、さらにキヌサヤエンドウへと移っていきました。作るものが変わるたびになぜ変えるのかという議論が家の中であったわけではないですが、周りの産地の動きや市場の様子を見ながら、自然とそうなっていった、という感じだったと思います。また、観葉植物が入ってきた時代もありました。切り花や観葉は野菜とはまた違う流通で、三宅島でも可能性があるじゃないかという空気があった時期です。その時代でこの島で農業を続けるために、何を作ればいいのかを探し続けてきた、その積み重ねだったと思います」
「量では勝てない」という現実
― 三宅島で農業を続ける中で畑に立っているときと、市場に出したときとで感覚が大きく変わる瞬間があったのではないでしょうか。その違いをご自身の経験として聞かせてもらえますか。
「やっぱり、量ですね。三宅島で作れる量には、どうしても限りがあります。
キヌサヤエンドウを中心に、夏はスイカやかぼちゃ、きゅうり、なす、ピーマン。冬になれば、キャベツやブロッコリー、カリフラワー。一通りの野菜は作りますけど、どれも島内で売る分が基本になります。畑としては決して手を抜いているわけじゃないのですが、出てくる量はどうしても小さい。それが三宅島の農業の現実だと思います。それで、その野菜を市場に出してみると、また別の現実にぶつかるのですよね。一人で十キロ、二十キロ出したところで、愛知とか、向こうの大きな産地からトン単位で荷物が入ってくる。そうなると、競りの順番が回ってくる頃には、もうほとんど値段が決まってしまっている。結果として、最後の方に回されて売れないわけじゃないけど、単価が取れないという状態になる。一生懸命作っても、その努力が値段に反映されにくいのです。だから、市場に出せば何とかなる、という感覚は、三宅島ではなかなか持てない。量で勝負するやり方は最初から成り立たない。その現実を、野菜を作って、市場に出してみて、身をもって分かった、という感じです」
─ お話を聞いていると作り方や努力だけではどうにもならない、別のところにある壁のようなものも感じます。そのあたりを、現場に立ってきた実感として、どう受け止めてこられましたか。
「三宅島で農業をやっていると、本土の大きな産地と同じ土俵に立とうとしている自分たちをどうしても比べてしまうのです。でも、冷静に考えると、最初から条件が違いすぎる。畑の広さも、人の数も、集められる量も流通に乗せる力も違う。その中で、同じやり方をしていたら結果は見えている、という感覚がありました。そもそも、同じことをやる前提が違っているのです。だから、三宅島は、大きな産地と同じことをやっていたら残れない。それは諦めというより、現場に立ってきた中で自然と行き着いた結論でした。じゃあ、どう違う道を選ぶのか。何を作って、誰に届けるのか。そのことを考えないと、この島の農業は次につながらない。そういうところまで追い込まれていた、というのが正直なところです」
早稲田ミョウガを「守る」のではなく「引き受ける」
─ 早稲田ミョウガは、江戸東京野菜として知られながら、東京の畑では続けることが難しくなっている。その行き先として三宅島の名前が挙がったことをどんなふうに受け止めましたか。
「話が来たのは一昨年くらいだったと思います。最初に聞いたのは、東京ではもう暑すぎて、早稲田ミョウガの栽培が難しくなっているという現状でした。正直、その時点で、もう都市で続けるのは限界なのだなということは、感覚的に伝わってきました。気候の問題もあるし、畑の環境や担い手の問題もある。いろいろ重なって、これまで当たり前だった場所で作れなくなってきている、そういう話だったと思います。ただ、印象に残っているのは、文化財のように保存してほしということではなく、この先も作り続ける場所として引き受けてほしいという投げかけでした。それを聞いたとき、引き受けるということは、失敗も含めその先を背負うことになる。同時に三宅島の農業が違う役割を担う可能性がある、そんなふうにも感じました。守るのではなく、次につなぐ場所として託された、そういう受け止め方をしたというのが一番近いと思います」
― 「守る」のではなく、作り続ける場所として引き受ける。その前提に立ったとき、いま、早稲田ミョウガの畑はどんな状態にありますか。現在の様と、ここまでやってきた手応えを聞かせてください。

「最初から試しにという話ではありませんでした。絶やしちゃいけないという前提で来ている話ですから。今あるのは三十株くらいです。決して多い数ではないし、まだ、できたと言える段階でもありません。今はちょうど地上部はすべて枯れていて畑を見ても何もないように見える状態です。知らない人が見たら、本当に育っているのかと不安になるかもしれません。でも、ミョウガはそういう作物です。地上がなくなっても、地下ではちゃんと生きている。三月の後半から四月にかけて、また芽が出てくるはずだと思っています。だから今はこの何もない時間も含めて、引き受けた責任の一部なのだと考えています」
― 火山島である三宅島の土に対して、これまで農業をやってきた中で、これは他とは違うなと感じてきた点があったと思います。その感覚は、早稲田ミョウガを受け入れる判断にどうつながっていきましたか。
「三宅島で長く農業をやっていると土については理屈より先に感覚が身につきます。火山島の土って、見た目からして本土とは違うのです。黒っぽくて、軽くて、雨が降っても、いつまでも水が溜まらない。ちょっと強い雨が降っても、数時間もすればまた畑に入れるようになる。一方で、同じ島の中でも場所によって違いがあって排水がいいところもあれば、保水性が強いところもある。そういう違いを見ながら、この作物はここ、これはあっちの畑がいいと選んできた、という積み重ねがあります。早稲田ミョウガの話を聞いたときも、専門的なデータを見たというより、まず頭に浮かんだのは、この島の土の感触でした。水はけがよくて、根が蒸れにくい。しかも、夏は本土ほど暑くならない。そう考えたときに、もしかしたら持つかもしれないという感覚が自然と出てきたのです。だから、三宅島だから特別なことができるというより、これまで島の土と向き合ってきた中で、この条件なら合うかもしれないと思えた。それが早稲田ミョウガを引き受ける判断につながっていったという感じです」
技術よりも先に問われる姿勢
― 早稲田ミョウガの栽培に取り組むにあたって、最初からご自身のやり方を貫くのではなく、どんな姿勢で向き合おうとされてきましたか。栽培方法との付き合い方について、考えていることを聞かせてください。
いまは、井之口さん(地下茎の発見と育種に関わり早稲田ミョウガをよみがえらせた練馬の農家、井之口喜實夫氏)に電話をして教えてもらいながらやっています。せっかくいただいた苗を無駄にしてはいけないので、失敗しないようにまずは、井之口さんがどう作ってきたのか、そのやり方を、できるだけそのままなぞる。うまくいくかどうかは別として、同じ条件でやってみないと、何が原因なのかも分からないですから。植え付けも、聞いた通りにやっています。芽は、二十㌢くらい下に入れて土を戻す。芽がある程度伸びてきたら土寄せをして敷き藁を敷く。自分なりの工夫をするのはもう少し先の話。まずは数年間教わった通りにやって三宅島の畑でどう出るのかを見る。その結果を引き受ける。いまはその段階にいるという感じです」

大年さん (令和7年4月)

希少性の高い野菜という、もう一つの選択
― 量では勝負できない、市場に乗せても報われにくい。そうした現実を踏まえたうえで、大年さんは希少性の高い野菜の生産にも取り組むようになります。その発想は、どんな経験や判断から生まれてきたのでしょうか。
「いま取り組んでいるのは、国内でもまだ作り手が少ない野菜です。業者の方から、これなら、この値段で買えると具体的な話をもらったのが始まりでした。値段が先に見える、行き先が分かっている。それだけで、農業のやり方はずいぶん変わります。作ってから売り先を探すのではなく、必要とされているものを必要な分だけ作る。その方が、三宅島の規模には合っていると思ったのです。いまは数人で組んで試験的に作り始めている段階です。まだ量は多くありませんが、少なくとも作ったものがどこへ行くのか分からない、という不安はない。それは、島で農業を続けていく上ではかなり大きな違いだと感じています」
─ 早稲田ミョウガのように、絶やしてはいけない野菜がある一方で、希少性の高い野菜のように、きちんと収入につながる取り組みも進めています。この二つを同時に抱えながら、三宅島の農業をどう成り立たせていくのか。いま、どんなバランスを意識されていますか。
「根っこは同じで、三宅島がどうやって残るかという問いに向き合っているだけなのです。片方は、絶やしてはいけないものを次につなぐ仕事で、もう片方は、農業としてきちんと食べていくための仕事。役割は違いますけど、どちらか一方だけでは成り立たないと思っています。文化だけを守っても、暮らしが続かなければ意味がないし、稼ぐことだけを考えても、この島らしさがなくなってしまう。その両方を、同じ現場で引き受けるしかないという感覚ですね。だから、全部まとめて、三宅の農業をどう残すかという一つの仕事だと思っています」
噴火・全島避難という「断絶の時間」
― 2000年の噴火によって三宅島は全島避難という状況を経験しました。農業に携わってきた立場として、あの出来事とその後の時間を、どのように受け止めてこられましたか。
「避難先は八王子市の南大沢でした。期間としては、四年半です。その間は、造園土木の仕事をしていました。体を動かす仕事だったので畑仕事から完全に離れるという感じではなかったですけど、やっぱり農業とは違いますよね。一番きつかったのは、いつ帰れるか分からない、という状態が続いたことでした。先の見通しが立たない中で時間だけが過ぎていく。畑をどうする、来年は何を作る、そういう農業の時間軸が完全に止まってしまった感じでした。だから避難している間は、帰れるかどうかも分からない中で将来の農業の話を考えるのは正直、難しかったです。いま振り返ると、あの時間は、農業を一度失った期間でもあったし、同時に戻れるなら、もう一度ちゃんと畑に立とうと心のどこかで準備していた時間でもあったのかな、そんなふうにも思います」
いつ帰れるか分からない状況の中で、それでも戻る準備をするという選択をされました。迷いもあったと思いますが、あの時、大年さんの背中を押したものは何だったのでしょうか。
「噴火は、三宅では運命みたいなものなのです。島の噴火は本土の災害とは少し違って命さえ取られなければ、どうにかなる、という感覚があります。畑はやられるかもしれない。暮らしは止まるかもしれない。でも、生きていれば、また一からやり直せる。そういう前提で、島の人間は生きてきたのだと思います。だから避難中も、もう農業は終わりだとは思わなかった。戻れるかどうかは分からなくても、戻れる可能性があるなら、その時に備えておこう、という気持ちはありました。帰島に向けて重機の免許を取りましたし、畑を自分で作れるように、必要な準備を進めました。三宅で農業を続けるなら、それぐらいは当たり前のことだった、という感覚です。生きていれば、また畑に立てる。その前提で動いていただけだと思います」

後継者と、農業振興会という制度
─ いま、大年さんは三宅島農業振興会の代表という立場にあります。個人の農業ではなく、島の農業全体を預かる立場として日々考えていること、とりわけ大切にしている点は何でしょうか。
「やっぱり、組織を残すことです。農業振興会がなくなってしまったら、この島の農業は、それぞれがバラバラに頑張るしかなくなる。それでは、続かないと思っています。個人の努力だけでは限界があるのをずっと見てきましたから。後継者の話になると、どうしても厳しい言い方になりますけど、儲からないと人は来ません。気持ちがあっても生活できなければ続かない。だから順番としては、まず、今ここにいる農家がきちんと稼げる形を作ること。それが先だと思っています。農業振興会としては理念を掲げる前に現場が回る仕組みを作る。お金が回り、仕事として成立する。その姿を、まず残すこと。後継者は、その先に、結果としてついてくるものだと考えています」
食料安全保障としての島の農業
─ ここまで、三宅島で農業を続けてきた時間や、引き受けてきた判断について伺ってきました。それらを踏まえたうえで三宅島の農業がどんな役割を果たしていくべきだと感じていますか。
「東京に被害があっても東京には食べ物が入ってくるのですよね。どこかがやられても、別のところから必ず流れてくる。そういう仕組みが、都市にはあります。でも、三宅島は違う。東京に何かあったら島には食べ物が入ってこない。それは、噴火のときも、台風のときも、身をもって分かっていることです。だから、一番根っこにあるのは、せめて島で食べる分の野菜は島で作る、ということだと思っています。市場に出すとか、ブランドを作るとか、その前の話です。何かあったときに島の中で最低限、食べられるものがあるかどうか。それだけで、人の安心感は全然違う。だから、野菜の種は、必ず余分に冷蔵庫に入れてあります。使わないかもしれないけど、なくて困るよりはいい。非常時に植えるものがないという状況だけは、作りたくないのです。三宅島では暮らしを止めないための農業は、一番大事なところじゃないかなとそう感じています」
─ ありがとうございました。

今でも見事に作り続けている大年さん