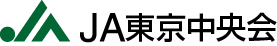【江戸東京野菜を語る ⑦ 】淀橋市場五十年 市場人 ・ 宇田川進が語る江戸東京野菜と流通の未来

東京都新宿区の大久保には多様な国籍の人々が集まる。眠らない街の中心にあって、なお人々の暮らしを静かに支え続けている場所がある。午前三時、都市が最も静まるその刻、白い吐息とともに働く者たちの声が重なり合い、確かな生命のリズムを刻む。この国の食流通を根底で支える現場、淀橋市場である。戦後の混乱期を経て東京の食を支えてきた同市場は、いまなお青果流通の要として機能し続けている。その歴史の変遷を現場の最前線で見つめ、体現してきた一人の市場人がいる。宇田川進氏(79歳)。淀橋市場仲卸組合副理事長として半世紀以上、市場を見続けてきた人物である。近年、宇田川氏が市場で取り組むテーマに江戸東京野菜の市場流通がある。とはいえ、市場流通の常識から見れば、江戸東京野菜は扱いにくい存在だ。数量は不安定、規格は多様、価格は一定しない。現代の大量流通や効率化の考え方とは相容れない。だが、「できるかできないかではない。やるべきことかどうかだ」―。市場とは何のために存在するのか、効率だけでは測れない価値とは何か。宇田川氏の言葉は、単なる流通現場の証言を超えて「食の公共性」と「地域の記憶」をめぐる問いを私たちに突きつける。本稿は、淀橋市場に生きる一人の市場人の半生をたどりながら、江戸東京野菜を通じて未来に向けた「市場」の価値や使命、そして東京の食を問うものである。
(聞き手:星槎大学客員教授・元東京都知事特別秘書 石元悠生)
本気で叩き込まれた「市場の原点」
― 宇田川さんは、昭和44年に淀橋市場を本体とする荷受会社へ入社され、半世紀以上をこの市場で過ごしてこられたと伺いました。当時、職業観が定まらない若い時期に数ある仕事の中から「市場」を選ばれるには何か決定的なきっかけや出会いがあったのでしょうか?当時の状況を思い出しながらお聞かせください。
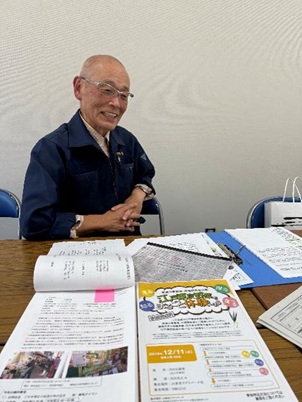
「市場との出会いは、計画して選んだものでも、就職活動の比較検討の結果でもありませんでした。きっかけは、ただ一人の先輩との縁です。高校時代にお世話になった方で東京農業大学の2年先輩でした。厳しいけれど、筋の通らないことを決して認めない人だった。その先輩が市場の荷受会社に就職したこともあり、『宇田川、迷っているなら俺の後についてこい』と。今振り返ると、誰と出会ったかで進路が決まることがある。そういうひょんなことから市場人として、もう50年余りこう生きてこられたということです」
― 市場人としての歩みは荷受けの仕事から始まったと伺いました。当時、どのような仕事を任され、どんな現場で経験を積まれていったのでしょうか。当時ならではの商いの空気も含めて具体的にお聞かせください。
「入社して現場には16年ほど携わりました。担当は主に地方から入ってくる青果、当時で言う地方蔬菜(そさい)部です。洋菜や果菜類を中心に、秋田や福島から四国、とくに高知まで産地ごとの顔が見える品を受け持ちました。仕事の要は競りです。当時は競りが販売の本流で買い手も多く、品物は基本的に競り台で勝負がつきました。

当時の淀橋は小売の八百屋がとにかく多い市場でした。最盛期には場内外で3,000店舗ほど。トラックがぎっしりで、場外の道まで溢れる賑わいでした。そういう環境では、こちらの声のかけ方ひとつ、順番の回し方ひとつで、場の温度が変わります。市場全体の屋台骨は白菜や大根、キャベツ、そしてジャガイモ、タマネギの大量入荷でした。日々の段取りは、入荷の見立て、品質の目利き、競りでの裁き、そして売り先との信頼づくりの積み重ねに尽きました。荷受けの仕事をしながら、伝票を渡したり並べ方を覚えたり、商品をどう見るか、値がどう決まるか、商売がどう動くか全てがここにありました」
都市の歴史と歩んだ淀橋での時間
─ 淀橋市場は、東京の都市構造の変化とともに独自の役割を果たしてきたと伺います。宇田川さんが実際に見てこられた範囲で、淀橋市場はどのように歩み、どのように変わってきたのでしょうか? 時代や周辺の街の動き、他市場との関係も含め歴史の手触りを教えてください。
「当時は、東京の中心に市場がある時代がまだ息づいていました。神田市場、築地市場、淀橋市場、そして豊島市場、そういう顔ぶれの中で、神田や築地を中核としながら、淀橋は外郭市場の筆頭として走っていた感覚があります。近くに青果物の集荷や販売、商品開発を行う東京多摩青果株式会社があり、互いに競い合い、切磋琢磨していました。今でこそ規模感に差は出ていますが、当時は本当にいい勝負をしていました。新宿の街並みも大きく変わりました。入社後2~3年して、西口の再開発が動き出し、京王プラザホテルが最初にそびえたつ。市場へ向かうトラックの列と、伸びていく高層の影を毎朝の荷の顔とともに見上げていました。街が変われば人の流れも変わる。八百屋の客筋、求める品揃え、値ごろ感とか、そうした肌触りが少しずつ揺れていく。その変化を、競り台の上から肌で感じてきました」
相手の仕事を成立させる、それが仲卸の責任
― 市場人としての土台を競りで築かれた後、40歳の頃に仲卸の道へ進まれました。競り人として市場の中心にいた宇田川さんが、なぜあえて別の領域に踏み出したのでしょうか?
「市場の動きや流通の構造はある程度見えるようになってきましたが、ある時、実際に野菜を扱う八百屋や料理人、その向こうにいる生活者の姿を見ていないことに気づいたのです。商いは、突き詰めれば責任を引き受ける仕事です。仲卸をやっていると、お客さんから本気で『頼む』と言われる瞬間があります。学校給食、病院、保育園、福祉施設、飲食店とか、どれも失敗が許されない現場です。『今日だけ入荷が少なかったので揃いませんでした、すみません』なんて言ったら、それはもう仕事じゃない。仲卸が扱うのは野菜という商品ですが、仕入れがなければ店は開けられない。給食に穴を開ければ、子どもに食べさせるものがなくなる。料理人に素材が届かなければ、その日の店は終わる。だから仲卸の本当の仕事は、物を渡すことではなく、相手の仕事を成立させることです。荷物を届けるだけなら誰でもできる。でも責任を引き受ける覚悟を持つことが仲卸の仕事だと思っています」
江戸東京野菜~市場合理で測れない価値との出会い
― 宇田川さんは、市場の実務に長く携わってこられたなかで、江戸東京野菜と出会い、深く関わるようになったと伺いました。そもそも、なぜ江戸東京野菜に目を向け、つながっていったのでしょうか?最初のきっかけや、心が動いた場面を教えてください。
正直に言えば、江戸東京野菜は『市場で日常的に回す』には難しい品です。値段が付きにくい、量のまとまりや規格が一般流通の感覚とズレ、仲卸に説明力が要る、いわばハンデを背負っている。それでも、どこかで気になっていました。市場の現場は儲からなければ扱わないという合理の世界ですから、意義だけでは動きません。転機は、ある日ポスティングで入ってきた一枚のチラシでした。『江戸東京野菜をまるごと体験しよう』という案内に興味を持ちました。まずは自分の目で確かめようと参加しました。千住ネギの圃場を訪ね、生産者の話を聞き、『これは値段や歩留りの話だけでは測れない』と感じたのです。参加者が市場関係者だけでなく、一般の方や飲食店の方もいて、同じ畑を見てそれぞれの立場で意見を交わす。その場の熱に当てられたのか『淀橋でも、できることはないか』とつい口にしてしまった。いや、口に出した時点で腹は決まっていたのでしょう。市場の合理の物差しだけでは拾えない価値が、江戸東京野菜にはある。だったら、やってみようと」
― 江戸東京野菜との出会いを経て実際にはどのような取り組みをしてきましたか? 市場の場づくり、イベント、販売の試行、普及活動など、できるだけ具体的にお聞かせください。
「まず、場をつくりました。淀橋は昔から八百屋が多い市場ですが、高齢化も進み、常の仕入れだけでは先細る。そこで2011年ごろから『イチバの日』を立ち上げ、毎月第3金曜日に小売の直売デーを設け、八百屋が攻めの売り方を試せる仕掛けを続けました。江戸東京野菜と正面から組んだのは、その後です。市場まつりの『宝船』展示脇に江戸東京野菜のサンプルを並べ、来場者に見てもらう。JA東京中央会の協力を得て講演会も開き、生産者の語りを市場に持ち込みました。まず視覚と言葉で伝えることに重点を置きました。販売の実証もやり、例えばイチバの日に合わせてごせき晩生小松菜を約70ケース手配し、最初は20軒ほどの八百屋に扱ってもらって、JA東京中央会と一緒にアンケートも取った。結果は悪くなかった。売れましたし、評価も得られた。ただ、補助事業の枠組みで価格を抑えられた面があり、日常の相場で継続できるかと言えば、そこにはやはり壁がありました」

― 効率や利益だけでは測れない価値を、どう市場で扱うのか。江戸東京野菜に取り組むことは、その問いと向き合う営みでもあったように感じます。江戸東京野菜に取り組む意味とは何だったのでしょうか?
「江戸東京野菜は特殊だからこそ、イベントや展示、語りを束ねる役が必要です。東京ウド、金町コカブ、馬込三寸ニンジンなど品目ごとの物語を仲卸がきちんと理解して試食、対面の言葉に落とす。八百屋が自分の言葉で語れるところまで伴走しないと流通には乗らない。正直、今も市場の通常流通はほとんどないと申し上げるしかありません。しかし、ゼロではない。市場まつりや各種イベントでの展示と試売、講演や現地見学、関係者同士の対話などを通じて火種を守っていくうちに扱える八百屋が少しずつ育つ。江戸東京野菜の価値は、歩留りや単価だけでは測れない。都市の記憶を食でつないでお客様へ橋渡しする。それが続けてきた仕事です」
効率ではなく「意味」を売る、 市場発の新しい流通モデル
― 近年、江戸東京野菜に対して新たな動きが生まれつつあります。たとえば都内の高級スーパーが「生産者とともに売り場をつくる」という思想のもと、江戸東京野菜を一堂に集めた販売企画に強い関心を示し、市場にも協力を求めていると伺っています。通常の大量流通とは異なる価値の伝え方を求められる挑戦であり、同時に市場としての存在意義が問われる局面とも言えます。こうした機会に対し、宇田川さんはどのような戦略で臨もうとしているのか、お考えをお聞かせください。
「江戸東京野菜は、単に商品として並べて売れば済む品物ではありません。一つひとつに物語があり、種の来歴や栽培の苦労、守り継ぐ人の営みが宿る。だからこそ『語れない者には売れない』野菜だと私は思っています。今回、その高級スーパーから打診があったとき、私は直感的に『これは逃してはいけない機会だ』と感じました。なぜなら、これは価格や効率では語れない価値を、都市の消費者に正面から問いかける場になるからです。しかも農家が店頭に立つという提案には、まさに江戸東京野菜の顔が見える関係と対話が含まれているからです。もちろん課題は山積しています。最大の難関は量が揃わないという現実です。しかし私は、そこにこそ野菜の本質があると思っています。大量に出回らないから価値がある。欠品が起きることすら本物の証として伝えねばなりません。できないことをごまかすのではなく、『できないという事実を価値に転換する』という戦略で臨むべきだと考えています。これは、江戸東京野菜を市場と産地、都市と農村をもう一度つなぎ直す仕事です。だから私は、この場に市場が関与することに大きな意味を感じています」
― 江戸東京野菜は、直売型の小規模流通が中心で市場流通には乗りにくいと言われています。それでも宇田川さんは、「市場こそが江戸東京野菜を広げる力を持つ」と語っています。では、なぜ「市場」なのかー。仲卸の努力だけではなく、市場という看板が必要だと考える理由をお聞かせください。
「私は、市場には産地を育てる使命があると思っています。江戸東京野菜は、確かに儲かる商材ではありません。手間もかかるし、安定供給も難しい。だから多くの仲卸は手を出したがらない。しかし、それを理由に背を向けてしまったら、市場の存在意義はどこにあるのか。市場が効率だけを追うなら、それはもう市場ではなくただの物流です。私は、ここを見誤ってはいけないと思っています。重要なのは、『市場だから広げられる』という事実です。仲卸がどれほど努力しても、個社の看板では影響力に限界があります。しかし市場が扱うとなれば話は変わる。市場には信用力があり、情報発信力があり、ネットワークがある。その力を使えば、江戸東京野菜を地域ブランドとして再生し、東京の食文化の中に正しく位置づけ直すことができるのです。江戸東京野菜は希少です。だからこそ、都市の歴史と食文化を象徴する存在になり得る。市場がその橋渡しを担う、その先頭に立ちたいと思っています」
― 江戸東京野菜の取り組みは、東京の食文化や地域の記憶を次代につなぐ試みであるべきと言われています。では、この取り組みを今後どのように広げ、どのような形で未来へつないでいこうと考えておられますか。
「これからやるべきことは仲間を増やすことです。 江戸東京野菜の取り組みは、淀橋市場だけが頑張っても難しいです。東京には多くの市場があります。そこにいる市場人が本気で連携すれば必ず大きな力になるはずです。そして市場だけではなく、八百屋や飲食店に料理人、学校の給食現場、そして行政、生産者、消費者がつながってこそ本当の意味での『食の文化』は続いていくと思います。そのために必要なのは、農や食に関わる一人ひとりが自分ごととして参加すること。その輪を広げていくのが市場の重要な役割だと思っています」
―― ありがとうございました。