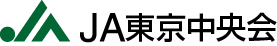【江戸東京野菜を語る④】語る料理人「押上 よしかつ」佐藤勝彦氏~東京の味と農が響きあう場で

東京スカイツリーの足元、墨田区押上の路地裏で暖簾を掲げる「押上 よしかつ」。この小さな店の厨房に立つ佐藤勝彦さん(57)は料理人であると同時に江戸東京野菜の〝語り部〟であり、都市と農をつなぐ架け橋でもある。そこには、食材が育まれた土地の文化や人の想いが「言葉」を通じて消費者へと手渡される。江戸東京野菜という固有の作物だけでなく、それを育むことのできる畑のある風景や担い手の存在、気候と土壌、そして消費者の意識をいかに維持し、次代へとつなげるかという問いが込められている。料理は「食べる」だけの行為ではなく、「語る」行為であり、「出会う」場でもある。その手段として、店内の椅子や棚には多摩産材を使用し、料理とともに東京産の酒とのペアリングも提案。「東京を五感で感じてもらう」というコンセプトが「押上 よしかつ」という空間を唯一無二のものにしている。本稿では、江戸東京野菜との出会い、語る料理の哲学、そして都市農業をめぐる未来への展望まで、佐藤さんの語りを通して東京の味と風景の本質に迫る。
(聞き手:星槎大学客員教授・元東京都知事特別秘書 石元悠生)
「東京で育った自分」が選んだ料理人という道
― 都市と農業が共存する環境で育ったと伺いました。まずは、そうした原風景がどのようなものであったのか、料理人としての原点につながる思い出から教えてください。

「東京都練馬区で生まれ育ちました。今でこそ住宅街としてのイメージが強い場所ですが、子どもの頃にはまだ畑があちこちにあって、夏になると直売所が開いて、採れたての野菜がずらりと並ぶような光景が日常でした。畑の横を通ると、土の香りが鼻をかすめる。トマトやきゅうりをかじると、ほんのり土の味がして、太陽の匂いもする。そういう記憶が、自分の中に深く残っています。都市の中に農があることを、特別なことだと当時は思っていませんでした。でも、振り返ってみると、あの環境こそが、いま私が東京の味とは何かを考えるうえでの原点になっているのではと感じます」
― 進学された大学では、どのような学びや経験が、現在のご自身に影響を与えましたか?
「大学では畜産を専攻し、牛や豚、鶏など、いわゆる家畜動物について学びました。都市で暮らす私たちは、便利な食生活の裏側にある現実を見落としがちです。つまり、生産と消費の断絶に強い違和感を覚えるようになったのです。 そうした疑問が後に都市農業や地域の食材に目を向けるようになりました。卒業論文は都市農業をテーマに選びました。地元でもある練馬には多くの直売所が点在していて、生産者の顔が見える販売スタイルが根づいています。けれど、そうした豊かな営みが、都市に暮らす人たちにあまり知られていない現実がありました。畑のそばを歩いているのに、その農業の営みが風景の一部として埋もれてしまっている。都市と農の間に存在するその目に見えない断絶こそが、自分の問題意識だったのではと思います」
― 卒業後は、すぐに料理の道へ進まれたわけではなかったのですね。当時はどのようなお考えだったのでしょうか?
「大学を出てすぐにサミットというスーパーマーケットに就職しました。そこでは店舗での品出しから売場づくり、惣菜部門の調理、さらには物流や発注の仕組みまで、食が消費者に届くまでの全体像を学びました。非常に勉強になる日々でした。ただその中で、どうしても心に引っかかっていたのが、『東京産の食材が、なぜこれほど棚に少ないのか』ということでした。自分が育った土地で、確かに畑があり、農家がいて野菜が作られているはずなのに、それが都市の流通に乗ってこない現実。30年前に感じたそのギャップが、自分にとって大きな問いとして残り続けたのです。そうした経験が、やがて『だったら自分がその接点になろう。東京の食材を料理という形で伝えよう』という思いにつながっていったのかなと」
― その後、飲食業に転じたきっかけは何だったのでしょうか。ご自身でお店を構えるという決断には、どのような思いがあったのか教えてください。
「26歳の時にもんじゃ焼の小さな店を構えました。きっかけは、当時出会った東京産のソースの味に感動したことです。このソースは甘みが少なく、スパイス感があり、旨味と色がしっかりしていました。『これこそ東京の味だ』と直感して、これを使った料理をしたいと思ったことです。もう一つは喫茶店のマスターに憧れていたことでしょうか(笑)。最初は手探りでのスタートでしたが、地元食材を活かした料理を出してみたいという気持ちははっきりしていました。しかし食材に関しては、東京産はおろか国産のものも使えないで、自分の思いと現実のギャップにもやもやとしていました。また、もんじゃ焼の焼き方については、うるさい人ばかりでした。

お店の前の東京食材使用店のプレートと地場産品応援の店の緑提灯
この辺とあっちの通りの向こうとはどう違うとか。さらに形が違うとか。だから逆に口を出さなかったのです。2001年から現在の場所(押上)に移転してもんじゃ焼の居酒屋スタイルに変更しましたが、今は、お客さんにはもんじゃ焼のルーツを「知識」として入れています。基本はセルフなのですが、お客さんの8割は焼けないなので焼いてあげることにしています。観光地になってしまったことが要因ですが、結局地元の味を表現することは単なる地産地消ではなく、東京に根ざした食文化を語ることだと感じています」
土地と記憶が宿る江戸東京野菜との出会い
~生産基盤の重要性を問う
──江戸東京野菜と出会ったきっかけについて教えていただけますか。その後、どのように料理に取り込んでいかれたのでしょうか?
「最初の出会いは2009年、墨田区の第一寺島小学校の創立百三十周年イベントのときでした。地域の子どもたちが地元の歴史を学ぶ取り組みの中で、かつてこの土地で栽培されていた寺島ナスの栽培を復活させたという話を知人に聞いたことをきっかけに江戸東京野菜の使用を本格的に始めました。まず始めたことは、メニュー構成を柔軟にしました。例えば、サラダだったら、レタスとキュウリとトマトのサラダ、ツナサラダとしていたのを全部やめて『季節の野菜サラダ』と一言にまとめました。言葉から入ることで、少量しか入手できない野菜も活用できるようになりました。また、小松菜の焼きそばなど通年で提供できる、使えるものに工夫しています。分かりやすく言うと、大皿の上に江戸東京野菜をのせて、このお皿を東京産の野菜と言う皿にして、その中の伝統野菜っていう分野の野菜がここですよと話して置けば、お客さんにとっても分かりやすいでしょう」

― とはいえ、東京産の野菜や江戸東京野菜の提供とはいっても、最初はかなりご苦労されたと伺いました。お客さんとの間でどのようなエピソードがありましたか?
「東京にいるから、東京に来たからということで東京産の食材を食べたいというお客さんが増えてきたのは嬉しいことでしたが、最初はお酒も含めてさんさんたる言われようでした(苦笑)。これを聞いたら生産者の方は涙が出ると思うのですが、お客さんに『東京産の野菜です』と説明すると、『こんな排気ガスまみれのものを食わすのか』と言われたりしました。そもそも東京産野菜というものを知らないわけですので仕方ないのですが、料理を出すときに生産者がどのようにして作っているのかをきちっと説明できた時には納得して理解してくれました。東京産の野菜を集めるコンセプトで、それを料理に転用することと、その中で江戸東京野菜を埋め込んでいったということです。なので、江戸東京野菜を料理として出す時に、その組み立て方にはいろんなやり方があると考えています」
― 飲食店が江戸東京野菜の良さを理解した上で、調理の技術を駆使して料理を作れるということが大事ということでしょうか?生産者側との連携が重要になってきます。
「江戸東京野菜はもちろん大事です。しかしながら、その手前の一般野菜がもっと大事です。まずは生産者が一般の野菜などの農産品を作れるベースがないと江戸東京野菜は作れないのです。こうした基盤がきちんと残っているのかどうかが大事だと思います。生産者に対して江戸東京野菜は価値が高いので生産を促すだけでなく、生産者は経済作物として一般野菜をきちんと生産していくことがまずは重要だと思います。江戸東京野菜はそんなに簡単に作れるものではないので、プラスアルファ的な考えで生産に取り組んでいってほしいです。飲食店は、それを生かした料理を作れるところで、適正な価格で購入できることのほうが大切だと考えます。それが結果的に東京の農業全体や農地の確保や存続につながっていくことが理想です」
都市農業の〝語り部〟としてあるべき姿とは何か
― 「料理人は語り部だ」とおっしゃっています。これは非常に印象的な言葉ですが、どのような思いや経験から、そうした考えに至ったのでしょうか?
「料理を提供するという行為は、ただ食材を調理して出すだけではなく、生産者が丹精込めて育てた野菜には、その土地の土壌や気候、栽培の工夫、担い手の想いといった、見えない物語が必ずあります。しかし、それは皿の上にポンと載せただけでは伝わらない。だからこそ、料理人がその物語を受け取り、それを翻訳してお客さまに伝えることが必要だと考えています。例えば、亀戸大根と練馬大根、大蔵大根となんでこうも違うものか説明してほしいとお客さまに聞かれると、丁寧にその違いを説明します。説明のポイントは、地形、歴史、後は都市形成学の3つになります。都市形成学は、要するに流通だったり、どこまでが江戸
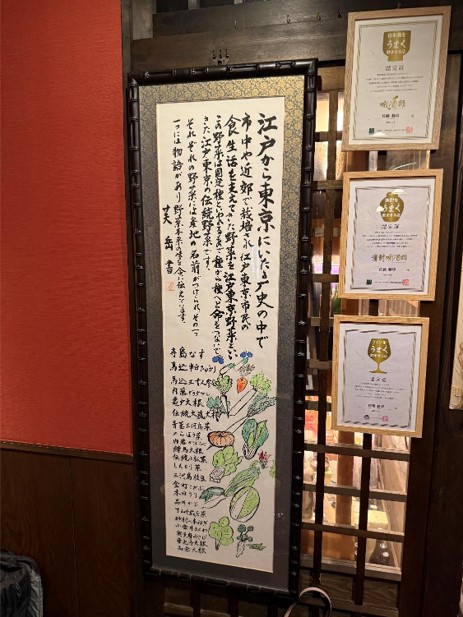
だったのかといった要素も加味して江戸東京野菜が産地化していく理由があることをお伝えします。小松川が小松菜の産地になった理由を考えても、船で運びやすいとか、地質的に粘土層が浅いところで作っているとか、複合的に産地形成のポイントをお伝えしています」
― 背景を伝えることで、味わいが深まると感じていらっしゃるのですね。その具体的な実感や、料理人としての工夫について教えてください。

「背景を知ってもらうことで、料理の味わいは格段に深まると実感しています。単に『おいしい』という評価だけではなく、『どうしておいしいのか』『どこで、誰が、どうやって育てたのか』といった情報が加わると、味覚が記憶と結びつきます。たとえば、寺島ナスは、皮が厚めで小ぶりで身がしまっている特徴があり、基本的には油で揚げて使いますが、皮目に切れ目を入れて火の通りを調整し、細かく刻んで生で使うとコリコリとした食感が楽しめます。お客さまには、野菜の特徴を説明したうえで『かつての東京の味』として受け取ってもらいたいという思いから、食材の背景をきちんと伝えることもまた料理の重要な一部だと考えています」
― そこまで強い思いで都市農業にこだわり続けていらっしゃるのはなぜでしょうか。その根底にある考えやご自身の体験を交えて、お聞かせいただけますか?
「料理を通じて『農のある都市』を実感してもらうことが、料理人としての役割の一つだと考えます。ただ調理して提供するだけではなく、その背景にある土地や人々の努力、季節の営みを料理の中に映し出す。そうすることで、食べる側の意識や感性も少しずつ変わっていくと信じています。そのために、私はできるだけ農家さんと直接会って話を聞くようにしています。どんな思いで育てているのか、今年の気候で野菜にどんな影響があったのか、そうした背景を聞いたうえで、その野菜にふさわしい表現を料理で形にしたい。単に農産物を使うということにとどまらず、そうした姿勢を店のお客さまにも伝えていくことが重要だと感じています。料理を味わうことを通じて、「東京の農」に思いを馳せてもらえたら、それが都市農業を支える意識づくりの一歩になると信じています」
― 東京の酒とのペアリングにも力を入れておられるとか。どのような意図や工夫があるのか、具体的に教えていただけますか?
「料理を通じて東京の風土や文化を伝えたいと考えていますが、その中で東京産の酒というのは非常に大きな可能性を秘めていると感じています。たとえば、江戸東京野菜の繊細な味わいや香りを引き立ててくれる東京の日本酒や焼酎、ワインと組み合わせることで、料理と酒が互いに響き合い、一層深い味わいの体験が生まれます。実際に、野菜の持つ苦味や甘味、香りの立ち方に応じて、酒の種類や温度、注ぎ方を変えることもあります。そうしたペアリングを通じて、『東京の野菜と酒が、こんなにも相性がいいのか』と驚かれるお客さまの表情を見ると、とても嬉しいですね。野菜と響き合う東京の日本酒や焼酎との組み合わせを提案することで、味覚だけでなく香りや余韻も含めて東京の風土を五感で体験してもらえると思っています」

料理人が語る江戸東京野菜のこれからとは
― 江戸東京野菜を未来へつなぐには何が必要でしょうか。単に品種を守るということだけではなく、料理との兼ね合いからもどのような視点が大切だとお考えですか?
「農家が畑で汗を流し、命を育てる。その努力の先にある食材を、最初に手に取り、調理し、物語としてお客さまに届けるのが私たち料理人です。単なる提供者ではなく、共に支える者として都市農業の持続に関わっていくことが、これからの料理人に求められる役割ではないでしょうか。飲食店が東京の農産物の価値をしっかり理解し、それを料理に活かし、背景にある思いや風景を語りながらお客さまに届けていく。お客さまがそれに価値を感じ、継続的に応援してくれることで、都市農業は経済的にも文化的にも成り立っていきます。飲食店が価値を見出して仕入れ、伝える。そしてお客さまがそれを支持してくれる。そういう循環ができて初めて、都市農業は成り立つと思います。そのうえで、郷土料理とはその地域で生産されている食材で作られ、それをいかに美味しく食べるかという知恵や工夫が必要となります。『東京のものを食べた』という良い体験をもっと多くの方に届けたいと考えています」
―― ありがとうございました。
※「押上よしかつ」店舗情報
住所:東京都墨田区業平5‐10‐2
電話:03‐3829‐6468