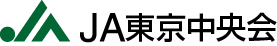【江戸東京野菜を語る①】伝統野菜「練馬ダイコン」を次世代へ~都市農業の現場から守り続ける“江戸の味”~「ファーム渡戸」農園主、渡戸秀行さん

練馬ダイコンが、なぜ「伝説の野菜」と呼ばれるのかをご存じだろうか。かつて全国に名を馳せながらも、その姿を消しかけた江戸東京野菜(注1)のひとつ「練馬ダイコン」(注2)。今、その味と価値を都市農業の中でよみがえらせている一人の農家がいる。江戸時代中期から続く農家で練馬区にある「ファーム渡戸」の農園主・渡戸秀行さん(59)だ。かつては姿を消しかけた練馬ダイコンが、なぜ今、改めて注目され、飲食店や消費者に求められているのか。そして都市農業という厳しい環境の中で、江戸東京野菜を守り育てるとはどういうことなのか――。固定種、直売、生産技術の進化など、東京・練馬の地で土と向き合う日々から見えてきた“未来に残すべき農業”の姿に迫った。
(聞き手:星槎大学客員教授・元東京都知事特別秘書 石元悠生)
江戸東京野菜との出会いと挑戦の始まり
― 渡戸さんが農業に携わるようになったきっかけを教えてください
「26歳で就農し、それ以来、練馬区で直売型農業を続けています。わが家は江戸時代中期ごろから続く農家です。当時、このあたりは徳川家の天領で、税負担が軽く、農業で生計を立てやすかったと聞いています。直売を開始したのは昭和50年代ごろで祖母が始めたのが最初になります。私が子どもの頃はキャベツ中心の栽培でしたが、大産地との競争が激化し市場出荷では採算が合わなくなったため、徐々に直売型へと移行しました。現在は約30種類の野菜を栽培しています。唐辛子や大根、小松菜、キャベツ、ブロッコリー、枝豆、トウモロコシ、人参、ジャガイモなど、幅広く手がけています。」

― 直売型農業の魅力とは何でしょうか

「やはり“顔の見える野菜”という点が大きな魅力です。自宅の裏の畑で採れた野菜を直接販売することで、お客様は新鮮な野菜をすぐに手に入れて、すぐに食べることができます。農家としても出荷の手間や手数料がかからず、効率的です。現在では、東京都内の多くのJAで直売所が整備され、多くの農家が直売に取り組んでいます」
― 江戸東京野菜との出会いはいつだったのですか
「平成初期に“江戸東京野菜”という言葉に触れました。当時はまだ種がなかなか手に入らなかったのですが、ある方が“馬込半白キュウリ”(注3)の種を配布していて、自家採種を勧められたのがきっかけです。珍しいからやってみようという気持ちで始めました。現在、栽培面積としては内藤トウガラシ(注4)が一番多いですが、生産量では練馬ダイコンが最も多いですね。通年ではごせき晩生小松菜(注5)も多く育てています。こちらは一年中栽培できるのが特徴です。」
練馬ダイコンの〝誇り〟と再生
― 練馬ダイコンの栽培を始めたきっかけは何ですか
「最初は自家消費用として栽培していました。販売用ではなく、ご近所に配る程度でしたね。本格的に販売するようになったのは、ずっと後になってからです。半白キュウリは病気に弱く、採算が合いませんでした。ピークが1〜2週間しかない上、うどんこ病(注6)にかかって売り物にならないことも多かったです。一方、練馬ダイコンは保存性が高く、加工にも向いていたため、徐々に扱いが増えていきました。」
― 練馬ダイコンの強みと弱みは何ですか
「やはり“地名が付いている”というのが地元の誇りにつながります。例えば、小松菜は江戸川区・小松川が発祥なので、練馬で作るのはちょっと気が引けるところもあります(笑)。でも練馬ダイコンは地元の名が冠されているので、自信を持って栽培・販売できます。ただし、一般的な大根は春と秋の年2回作れますが、練馬ダイコンは秋に1回だけという点が難しさですね。」
― 時期、練馬ダイコンの生産が減った理由は
「昭和後期から平成初期にかけては、練馬ダイコンがほとんど作られていませんでした。収穫に手間がかかるため、農家にとっては大きな負担だったんです。でも、当時の練馬区長が“練馬には、かつて全国的に有名だった練馬ダイコンがあるのに、なぜ今はないのか”と問題提起され、そこから『練馬ダイコン引っこ抜き大会』などの地域振興事業が始まり、再び注目されるようになりました。」

尾張大根と練馬の地大根との交配から選抜・改良されたもの。享保年間(1716〜1736)には練馬大根の名が定着した
― 練馬ダイコンの生産環境や栽培技術に変化はありますか
「令和に入り、生産技術と資材の進歩は著しいです。たとえば、45センチまで耕せる“深耕ロータリー”付きのトラクターを導入したことで、大根がまっすぐ深く育つようになりました。堆肥や肥料も改良され、病気のリスクも減っています。こうした環境整備のおかげで、練馬ダイコンも元気に育つようになりました。」
伝統野菜の価値「継承」に欠かせない哲学とは
― レストランなどの評価はいかがですか
「非常に好評をいただいています。特に、種まきを1カ月遅らせて育てた冬の練馬ダイコンは、1〜2月にかけて程よく育ち、Mサイズ〜Lサイズになります。細胞が若く、みずみずしく、青首大根とは異なる辛味のある白首大根として、料理人にとっては個性的で魅力的な食材です。飲食店のシェフが工夫して新しい料理を提案してくださると、生産者としても非常に励みになります」
― 消費者の反応はいかがですか
「練馬には農家が多いので、江戸東京野菜の栽培によって他との差別化が図れるという手応えがあります。例えば、スーパーで売っている小松菜よりも色が薄く、見た目は折れやすいごせき晩生小松菜ですが、食べるととても柔らかく美味しいと好評です。練馬ダイコンも12月ごろになると、“青首ではなく練馬ダイコンがほしい”というお客様が増え、10本・20本まとめて購入される方もいます。都内で伝統野菜が今も作られていることを知らない方も多く、遠方から買いに来られることもあります」

― 江戸東京野菜の伝統を守るうえで、大切にしていることは
「やはり“土づくり”が基本です。種をまく前の準備で、収穫の成否はほぼ決まります。堆肥を入れ、深く耕し、環境を整えてから種をまくと、もう7割方は勝負が決まったようなものです。また、江戸東京野菜専用の販売スペースを確保することで、通常の野菜との違いを明確に打ち出し、差別化を図ることも重要だと考えています。収益につながらなければ継続は難しいですから、“練馬ダイコンを作ると収入が上がる”という実感が得られるような流れを作ることが、伝統の維持にもつながると思います」
― 最後に、練馬ダイコンの未来についてどのようにお考えですか
「練馬ダイコンは、ただの伝統野菜ではなく、今も進化を続けている“生きた野菜”です。都市農業の中で地域の誇りや味を伝えていくとともに、料理人がその魅力を引き出してくれることで、食べ方の幅も広がっています。練馬ダイコンに限らず、地元で栽培されている野菜を消費者の皆さまに少しでも多く食べていただけることが、農家の応援になり、農地を守り、ひいては未来につながると信じています。」
―― ありがとうございました。
注1 江戸東京野菜:種苗の大半が自家採種または近隣の種苗商により確保されていた江戸から昭和中期(40年代) までの野菜。それぞれに物語があり、現在52種類(2023年10月現在)がJA東京中央会により認定されている。
注2 練馬ダイコン:尾張大根と練馬の地大根の交配から選抜・改良され、享保年間(1716~1736)には、練馬ダイコンの名が定着。徳川綱吉が栽培を命じたとされている。
注3 馬込半白キュウリ:大井胡瓜を改良したものであり胡瓜と瓜を掛け合わせている。明治30年頃に始まり、改良を重ねて節になる形になったのは明治37~38年頃である。
注4 内藤トウガラシ:内藤家の菜園(後の新宿御苑)から広がった野菜の一つ。品種は八房(やつふさ)トウガラシ。江戸の食に欠かせない七色唐辛子等で親しまれた。
注5 ごせき晩生小松菜:八代将軍、徳川吉宗が小松川村へ鷹狩りに出かけた際に食べたすまし汁に入っていた青菜をとても気に入り小松菜と名付けたとされる。
注6 うどんこ病:植物の葉や茎などに小麦粉を振りかけたように白い粉状のカビが生じる病気。植物の成長を阻害し、ひどい場合には枯死に至ることもある。
(いずれもJA東京中央会「江戸東京野菜ガイド」などを参照)